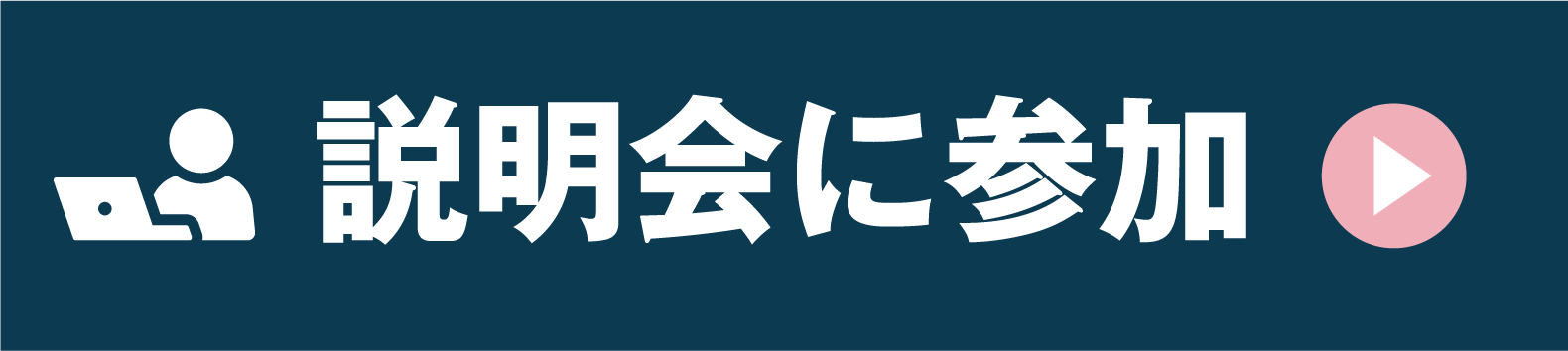フランチャイズニュース
フェアやイベントの出展情報、出店可能エリアなど、ガッツレンタカーフランチャイズビジネスに関するお知らせをご案内いたします。
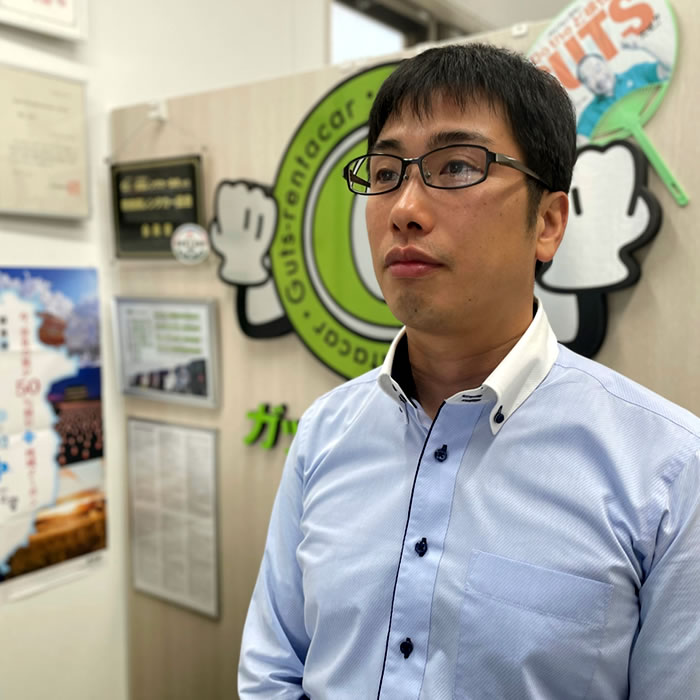
フランチャイズオーナーは儲からない?独立開業で失敗しないための全知識

将来のために独立を考え、フランチャイズに興味を持ったものの、「オーナーは儲からない」「本部に搾取されるだけ」といったネガティブな噂を耳にして、不安になっていませんか?
家族のためにも失敗は許されないけれど、このまま会社員を続けても先が見えている…そんな葛藤を抱える方は少なくありません。
この記事では、フランチャイズ経営の成功と失敗を知り尽くした専門家が、データと数々の事例に基づき、「フランチャイズは儲からない」という噂の真相を徹底的に解明します。
この記事でわかること
- 噂の真相:フランチャイズの成功率70%という客観的データとリアルな年収
- 失敗の根本理由:多くのオーナーが陥る5つの共通点
- 危険な本部の特徴:契約前に見抜くべき「儲からないフランチャイズ」の見分け方
- 成功へのロードマップ:失敗リスクを回避し、成功確率を高める5つの具体的ポイント
単なる成功事例だけでなく、失敗のリスクやその回避策まで深く掘り下げることで、あなたがフランチャイズという選択肢を冷静に判断するための材料を提供します。
この記事を最後まで読めば、漠然とした不安から解放され、自信を持って次の一歩を踏み出すための具体的な知識と判断基準を手にすることができるでしょう。
【結論】フランチャイズオーナーは「儲からない」という噂の真相
「会社員を続ける将来に不安がある。独立してみたいが、フランチャイズは儲からないと聞いて一歩が踏み出せない…」
多くの方が抱えるこのお悩み。結論から申し上げますと、「フランチャイズオーナーは儲からない」というのは、必ずしも正確な情報ではありません。
一部の失敗事例が誇張されて伝わっているケースも多く、実際には正しい知識と準備をもってすれば、会社員時代以上の収入を得ることも十分に可能なビジネスモデルです。
まずはデータと事実に基づき、この噂の真相を紐解いていきましょう。
「儲からない」は嘘?フランチャイズの成功率は70%というデータ
事業の成功を測る一つの指標に「事業生存率」があります。
実は、フランチャイズで開業した場合の5年後の事業生存率は約70%と言われています。
これは、個人でゼロから事業を立ち上げた場合の生存率(約40%)と比較して、非常に高い数値です。
このデータは、フランチャイズが「儲からない」どころか、むしろ「成功確率の高いビジネスモデル」であることを客観的に示しています。
この成功率を支えているのが、フランチャイズ本部が長年かけて築き上げてきた「成功のノウハウ」です。
確立されたブランド力、効果的な集客方法、質の高いサービス提供の仕組みなどを活用できるため、全くの未経験者でも事業を軌道に乗せやすいのです。
フランチャイズオーナーのリアルな平均年収とは
では、実際の収入面はどうでしょうか。フランチャイズオーナーの平均年収は、一般的に400万円~600万円が中心的な価格帯と言われています。
しかし、これはあくまで全体の平均値に過ぎません。
重要なのは、業種や経営規模、そしてオーナー自身の努力によって収入は大きく変動するという事実です。
| 業種 | 年収目安 | 特徴 |
| コンビニエンスストア | 700万円~ | 複数店舗経営で高収入を目指せるが、労働時間も長くなる傾向 |
| ハウスクリーニング | 500万円~ | 無店舗で開業でき、初期費用を抑えやすい。安定した需要が見込める |
| 学習塾 | 300万円~ | 生徒数に応じて収入が変動。地域での評判が成功の鍵 |
| 買取専門店 | 1,000万円~ | リユース市場の拡大を背景に、高い収益性が見込める人気業種 |
このように、多店舗展開に成功して年収1,000万円以上を稼ぐオーナーがいる一方で、残念ながら経営がうまくいかず、会社員時代の収入を下回ってしまうケースも存在します。
つまり、「フランチャイズ=儲かる/儲からない」の二択ではなく、成功の可能性はオーナー次第であると言えます。
なぜ「儲からない」という声がなくならないのか
これほど成功率が高く、実際に高収入を得ているオーナーもいるのに、なぜ「儲からない」という声はなくならないのでしょうか。
これには、主に3つの理由が考えられます。
- 失敗談のほうが目立ちやすい
成功しているオーナーは静かに事業を継続しますが、うまくいかなかった方の声はインターネットや口コミで拡散されやすい傾向があります。そのため、ネガティブな情報が過度に目立ってしまうのです。 - フランチャイズ特有の仕組み
毎月本部に支払う「ロイヤリティ」や、本部の方針に従う必要があるといった仕組みが、「本部に搾取されている」「自由がない」といった不満につながり、「儲からない」という評判に発展することがあります。 - 「加盟すれば安泰」という誤解
「本部のブランド力があるから何もしなくても儲かるはず」という甘い見通しで開業し、現実とのギャップに直面する方が一定数いることも事実です。経営者としての努力や覚悟が不足していれば、どんなビジネスでも成功は難しいでしょう。
つまり、「フランチャイズは儲からない」のではなく、「誰でも、何もせずに簡単に儲かるわけではない」というのが、この噂の正確な実態なのです。
なぜ?フランチャイズオーナーが儲からないと言われる5つの根本理由
フランチャイズ開業が高い成功率を誇る一方で、なぜ一部のオーナーは「儲からない」という現実に直面してしまうのでしょうか。
その背景には、単なる運や景気の問題ではなく、オーナー自身が陥りがちな共通の「根本理由」が存在します。
これらは、開業前に知っておくことで回避できるものばかりです。
フランチャイズというビジネスモデルの光と影を正しく理解し、失敗のリスクを徹底的に潰していきましょう。
理由1:想定以上に重くのしかかる「ロイヤリティ」
フランチャイズ経営において、利益を圧迫する最大の要因となり得るのが、本部に毎月支払う「ロイヤリティ」です。
これは、ブランド名や経営ノウハウを使用するための対価であり、避けては通れない費用です。
ロイヤリティの徴収方式は、主に2種類あります。
| 方式 | 内容 | メリット | デメリット |
| 売上歩合方式 | 毎月の売上に対して、決められた率(例:売上の5%)を支払う。 | 売上が低い時は支払額も少なくなる。 | 売上が伸びるほど支払額も増え、利益率が上がりにくい。 |
| 定額方式 | 売上に関係なく、毎月固定の金額(例:月5万円)を支払う。 | 売上が伸びれば、その分利益が大きく手元に残る。 | 売上が低い月でも固定額を支払う必要があり、経営を圧迫する。 |
特に注意が必要なのは、定額方式の場合です。
開業当初の売上が安定しない時期には、この固定費が精神的にも経営的にも重い負担となり、「働いても利益が残らない」という状況に陥りやすいのです。
契約前に、ロイヤリティが自身の事業計画や収支モデルにとって現実的な金額であるか、冷静に判断する必要があります。
理由2:本部のブランド力に依存しすぎた他責思考
「有名な看板さえあれば、何もしなくてもお客様は来るだろう」
これは、失敗するオーナーが抱きがちな、最も危険な幻想です。
フランチャイズ本部のブランド力は、あくまでもスタートダッシュを助けるための強力なツールであり、長期的な成功を保証するものではありません。
成功しているオーナーは、本部の提供するノウハウを最大限に活用しつつも、地域に合わせた独自のサービス展開や、顧客との関係構築、従業員育成といった「自分自身の経営努力」を怠りません。
「売上が伸びないのは本部のせいだ」と考える他責思考に陥った瞬間から、経営者としての成長は止まり、「儲からない」現実がすぐそこに迫ってきます。
理由3:甘い見通しによる運転資金のショート
事業の失敗原因として常に上位に挙がるのが「運転資金の不足」です。
これはフランチャイズ開業においても例外ではありません。
多くの開業希望者は、加盟金や店舗の改装費といった「開業資金」にばかり目が行きがちですが、本当に重要なのは開業後に事業を継続していくための「運転資金」です。
運転資金には、以下のような費用が含まれます。
- 人件費
- 原材料の仕入れ費
- 水道光熱費
- 家賃
- ロイヤリティ
事業がすぐに黒字化するとは限りません。
少なくとも3ヶ月~半年分の運転資金を自己資金として確保しておかなければ、想定外の事態が発生した際にすぐに行き詰まってしまいます。
「儲かる」前に資金が底を尽き、撤退を余儀なくされるケースは後を絶ちません。
理由4:契約内容の理解不足と本部のサポート体制のミスマッチ
「手厚いサポートがあるから安心」という言葉を鵜呑みにして契約し、後から「思っていたサポートと違った」と後悔するケースも少なくありません。
例えば、オーナーが期待していたのが「担当スーパーバイザーによる定期的な訪問指導」だったのに対し、本部のサポートが「マニュアルの提供とメール対応のみ」だった場合、大きなミスマッチが生じます。
契約書に記載されている「サポート内容」を隅々まで確認し、具体的にどのような支援を受けられるのかを事前に把握しておくことが不可欠です。
研修制度の充実度や、成功している他のオーナーとの交流機会の有無なども、本部を選ぶ上で重要な判断材料となります。
理由5:市場調査不足による需要のないエリアでの開業
フランチャイズ本部が提供するビジネスモデルがどれほど優れていても、出店する地域にそのサービスへの「需要」がなければ事業は成り立ちません。
例えば、高齢者が多い住宅街で若者向けのタピオカドリンク店を開業しても、成功は難しいでしょう。
本部から提供されるマクロな市場データだけでなく、オーナー自身が候補地の人口構成、競合店の状況、地域住民のライフスタイルなどを足で稼いで調査することが成功の確率を大きく左右します。
この手間を惜しむと、開業してから「お客様が全く来ない」という最悪の事態に直面することになります。
要注意!儲からないフランチャイズに共通する4つの特徴
フランチャイズでの失敗は、オーナー個人の資質や準備不足だけに起因するわけではありません。実は、ビジネスモデルそのものに「儲かりにくい構造」を内包しているフランチャイズ本部も残念ながら存在します。
大切なのは、契約前にその本質を見抜く「目」を持つことです。ここでは、特に注意すべき「儲からないフランチャイズ」に共通する4つの特徴を、具体的な見極め方とあわせて解説します。
特徴1:加盟金集めが目的で、開業後のサポートが手薄い本部
最も警戒すべきなのが、加盟店の成功による継続的なロイヤリティ収入ではなく、初期の加盟金で収益を上げることを主目的としているフランチャイズ本部です。
このような本部は、加盟店が増えること自体がゴールであるため、開業後のサポート体制が非常に手薄い傾向にあります。
【危険な兆候チェックリスト】
- 契約前に、成功事例や夢のある話ばかりを強調し、リスクや失敗事例について具体的に説明しない。
- 「今だけ」「限定〇名」といった言葉で、考える時間を与えずに契約を急がせる。
- 開業後のサポート内容が「マニュアル配布」「メール相談のみ」など、形式的なものに留まっている。
- 担当するスーパーバイザー(店舗指導員)の専門知識が乏しい、または訪問頻度が極端に少ない。
健全なフランチャイズ本部は、加盟店の成功が自社の成長に直結することを理解しています。
そのため、開業後の研修や経営指導といったサポート体制にこそ力を入れているのです。
特徴2:一時的なブームに乗っただけで、将来性のないビジネスモデル
数年前に社会現象となったタピオカドリンク店や高級食パン店。当時は大きな注目を集めましたが、ブームが過ぎ去ると同時に閉店が相次いだのは記憶に新しいでしょう。
このように、一過性のブームに乗り、短期的な収益だけを狙ったフランチャイズは非常に危険です。
開業時には順調でも、市場が飽和し、ブームが終焉すれば、一気に経営が立ち行かなくなります。
【将来性を見極めるポイント】
- リピート性:一回きりの利用でなく、顧客が繰り返し利用したくなるサービスか?
- 普遍的な需要:ブームに関係なく、日常生活の中で必要とされるサービスか?
- 事業の持続性:本部の事業が少なくとも5年以上継続しており、安定した成長を遂げているか?
目先の華やかさだけに惑わされず、そのビジネスが5年後、10年後も社会から必要とされ続けるかを冷静に見極める視点が不可欠です。
特徴3:競合が多く、価格競争に陥りやすい業種
コンビニエンスストアや一部の飲食店のように、すでに市場が成熟し、競合店舗がひしめき合っている業種も注意が必要です。
参入障壁が低い分、他店との差別化が難しく、最終的には熾烈な価格競争に巻き込まれてしまいます。
結果として、十分な利益を確保できず、「忙しいのに全く儲からない」という典型的な失敗パターンに陥るリスクが高まります。
また、本部によっては、加盟店の売上を増やすために近隣エリアに次々と新店舗を出店させる「ドミナント戦略」をとる場合があります。
これにより、既存の加盟店同士で顧客を奪い合う、共食い状態が発生することもあります。
契約前に、出店エリアを保護する「テリトリー権」が保証されているかを確認することも重要なポイントです。
特徴4:収益モデルが不明確で、オーナーの裁量が極端に少ない
説明会で提示される収支モデルが、「これはあくまで理想のケースで…」といった曖昧な説明に終始し、具体的な経費の内訳や、利益を確保するための明確な基準を示さない本部は信頼できません。
また、以下のようにオーナーの裁量が極端に制限されている場合も、自分の努力で収益を改善することが難しくなります。
- 原材料や商品の仕入れ先が厳しく指定されており、価格交渉の余地がない。
- 商品やサービスの価格設定が本部によって完全に固定されている。
- 地域限定のキャンペーンや独自の販促活動が一切認められていない。
フランチャイズは独立した事業主です。本部のノウハウに従うことは大前提ですが、その上でオーナー自身の創意工夫が活かせる余地がなければ、経営のやりがいを見出すことも、厳しい競争を勝ち抜くことも困難になるでしょう。
「儲からないオーナー」で終わらない!成功確率を高める5つのポイント
フランチャイズ経営は、「儲からない」と嘆く一部のオーナーがいる一方で、着実に成功を収め、安定した事業を築いているオーナーが数多く存在します。
両者の違いは一体どこにあるのでしょうか。
それは、開業前の準備段階における「5つの重要なポイント」を徹底できているかどうかに集約されます。
これらのポイントを一つひとつ確実に押さえることが、「儲からないオーナー」にならず、成功確率を飛躍的に高めるための鍵となります。
ポイント1:信頼できるフランチャイズ本部の見極め方
成功の土台となるのが、パートナーであるフランチャイズ本部選びです。
表面的なブランドイメージや甘い言葉に惑わされず、以下の客観的な基準で「本当に信頼できる本部か」を厳しくチェックしましょう。
【本部選びのチェックリスト】
- 情報公開の透明性:成功事例だけでなく、過去の撤退数や加盟店の平均的な収益モデルなど、ネガティブな情報も誠実に開示しているか。法定開示書面※を快く提供してくれるかは、その姿勢を測るリトマス試験紙です。
- サポート体制の具体性:研修内容、スーパーバイザーの巡回頻度、緊急時の相談窓口など、サポート体制が具体的かつ体系化されているか。説明会で担当者に質問し、明確な回答が得られるかを確認しましょう。
- 既存オーナーの声:本部に依頼し、実際に経営している複数の先輩オーナーと直接話す機会を設けてもらいましょう。現場のリアルな声ほど、信頼できる情報はありません。本部がこれを拒む場合は、何か隠したいことがある可能性を疑うべきです。
- 明確なビジョンと成長戦略:本部が将来どのような事業展開を目指しているのか、明確なビジョンを持っているか。企業の成長戦略に共感できるかも、長期的なパートナーシップを築く上で重要です。
※法定開示書面:中小小売商業振興法に基づき、フランチャイズ本部が契約前に加盟希望者へ開示することが義務付けられている書面。事業概要、契約内容、加盟店の金銭的負担などが詳細に記載されています。
ポイント2:失敗しないための事業計画と緻密な資金計画
「何とかなるだろう」という楽観的な見通しは禁物です。自身の事業を成功に導くための「設計図」となる事業計画を、数字に基づいて具体的に作成しましょう。
- 収支計画:目標とする売上だけでなく、人件費、家賃、ロイヤリティ、水道光熱費などのあらゆる経費を詳細に洗い出し、現実的な利益をシミュレーションします。最低でも「楽観」「標準」「悲観」の3パターンの収支計画を立てておくことで、不測の事態にも冷静に対応できます。
- 資金計画:開業時に必要な初期費用(加盟金、店舗取得費、内外装工事費など)に加え、事業が軌道に乗るまでの運転資金を最低でも6ヶ月分は用意しましょう。自己資金で不足する分は、日本政策金融公庫の創業融資など、低金利の公的融資制度の活用を検討します。
緻密な計画を立てるプロセスそのものが、事業のリスクを洗い出し、経営者としての解像度を高めるための最高のトレーニングになります。
ポイント3:契約前に必ず確認すべき重要事項
一度契約書にサインをしてしまうと、後から「知らなかった」では済みません。
専門家(中小企業診断士や弁護士など)に相談することも視野に入れ、以下の点は特に注意深く確認しましょう。
- 契約期間と更新条件:契約期間は何年か。更新は自動か、手続きが必要か。更新料は発生するのか。
- テリトリー権:自身の店舗の営業エリアが保証されているか。近隣に同チェーンの店舗が出店される可能性はないか。
- 中途解約時の違約金:万が一、契約期間の途中で廃業する場合、どの程度の違約金が発生するのか。
- 契約終了後の競業避止義務:契約終了後、一定期間は同業種のビジネスを営んではいけないといった制約(競業避止義務)の有無とその内容。
これらの項目は、将来的に自身の首を絞めることになりかねない重要なポイントです。
少しでも疑問があれば、納得がいくまで本部に説明を求めましょう。
ポイント4-5:オーナー自身の「経営者」としてのマインドセット・本部任せにしない、主体的な集客・運営戦略
ポイント4:オーナー自身の「経営者」としてのマインドセット
フランチャイズは、本部に雇用される従業員ではなく、自らの事業の全責任を負う「経営者」になるということです。
このマインドセットへの転換が、成功と失敗の最大の分岐点です。
本部から提供されるのは、あくまで成功確率を高めるための「道具」や「地図」に過ぎません。
その道具をどう使いこなし、地図を手にどこへ向かうかを決めるのはオーナー自身です。
問題が発生した際に「本部のせいだ」と考えるのではなく、「どうすればこの状況を打開できるか」と主体的に考え、行動する姿勢が求められます。
ポイント5:本部任せにしない、主体的な集客・運営戦略
本部の行う全国規模のマーケティング活動に頼るだけでなく、オーナー自身が地域に根差した集客戦略を展開することが、競合との差別化につながります。
例えば、
- 地域のイベントへの参加や協賛
- 近隣の店舗や企業との提携キャンペーン
- SNSや地域情報誌を活用した情報発信
- 顧客一人ひとりに合わせた丁寧な接客と関係構築
といった地道な活動が、やがて「あのお店だから行きたい」という強いファンを生み出します。本部が提供するマニュアルを遵守しつつも、その枠内で「自分だからこそできる価値」を追求し続けることが、長期的に儲かるオーナーになるための唯一の道と言えるでしょう。
【2025年最新情報】今、フランチャイズで儲かる可能性のあるおすすめ業種
フランチャイズで成功するためには、時代や社会の変化を捉え、将来性のある「伸びる市場」を選ぶことが極めて重要です。
かつて人気だった業種が、今も同じように儲かるとは限りません。
ここでは、2025年現在の日本の社会構造やライフスタイルの変化という、確かなトレンドを背景に、これからフランチャイズで開業するオーナーが大きな成功を掴む可能性を秘めた、おすすめの4業種を専門家の視点で解説します。
安定した需要が見込める「高齢者向けサービス(配食・介護)」
日本が直面する超高齢化社会は、ビジネスの観点から見れば、非常に大きく、そして確実な需要が存在する市場です。
特に、単身または高齢者のみの世帯が増加する中で、日常生活を支えるサービスへのニーズは今後ますます高まっていきます。
- ビジネスモデルの特徴:
- 配食サービス:栄養バランスの取れた食事を定期的に届けるビジネス。安否確認の役割も担うため、社会貢献性が高く、顧客との長期的な関係を築きやすい。
- 訪問介護・デイサービス:介護保険制度に基づく事業であり、国からの安定した収入が見込める。地域に密着し、質の高いサービスを提供することで、揺るぎない評判を確立できる。
- 儲かるポイント:
一過性のブームと無縁であり、景気の変動を受けにくいのが最大の強みです。一度顧客を獲得すれば、継続的な利用につながりやすく、安定した収益基盤を早期に築くことが可能です。未経験からでも、本部の充実した研修や資格取得サポートを活用して専門性を身につけられる点も魅力です。
社会的関心の高まりを追い風にする「リユース・買取専門店」
サステナビリティ(持続可能性)やSDGsへの関心の高まりは、リユース業界にとって強力な追い風となっています。
節約志向と環境意識の両方を満たす買取ビジネスは、今後も市場拡大が見込まれる成長分野です。
- ビジネスモデルの特徴:
- 総合買取:幅広いジャンルの品物を買い取り、再販するモデル。
- 専門特化型買取:ブランド品、貴金属、骨董品、トレーディングカードなど、特定のジャンルに特化することで高い専門性を発揮し、高利益率を狙うモデル。
- 儲かるポイント:
無店舗(出張・宅配買取)で開業できるフランチャイズが多く、店舗を持つ場合と比較して開業資金や固定費を大幅に抑えることが可能です。本部の持つ査定ノウハウや販路を活用することで、未経験者でも短期間でプロの鑑定士として事業を開始できます。フリマアプリの普及で「不要な物を売る」文化が定着したことも、ビジネスの機会を広げています。
店舗運営の手間が少ない「ハウスクリーニング・家事代行」
共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、「家事をアウトソーシング(外部委託)し、時間を買う」という価値観が急速に浸透しています。
特に、専門的な技術が必要なエアコンや換気扇のクリーニングは、プロに依頼したいという需要が非常に高い分野です。
- ビジネスモデルの特徴:
- ハウスクリーニング:専門の機材や洗剤を使用し、家庭では難しい箇所の清掃を行う。
- 家事代行:掃除、洗濯、料理など、日常的な家事を代行する。
- 儲かるポイント:
リユース業と同様に、無店舗・無在庫で開業できるため、低資金でスタートできるのが最大のメリットです。一度サービスを提供して顧客満足度を高められれば、定期契約やリピート受注につながりやすく、安定した収入の柱を築くことができます。コロナ禍以降、家庭内の衛生意識が高まっていることも、この業界の成長を後押ししています。
健康志向の高まりで伸びる「小規模フィットネスジム」
健康寿命への関心が高まる中、フィットネス市場は多様化の時代を迎えています。
従来の大型総合ジムだけでなく、特定のニーズに特化した小規模ジムが人気を集めています。
- ビジネスモデルの特徴:
- 24時間ジム:利用者の好きな時間に利用できる利便性を追求。スタッフの常駐時間を限定し、省人化運営で高い利益率を目指せる。
- パーソナルジム:専属トレーナーによるマンツーマン指導を提供。高単価ながらも、「結果にコミットしたい」という明確な目的を持つ顧客層に支持される。
- 儲かるポイント:
ターゲット顧客を絞り込むことで、大手との差別化を図りやすいのが特徴です。特に24時間ジムは、DX化による徹底した運営効率化のノウハウが本部によって確立されており、オーナーの負担を軽減しながら高収益を目指せるビジネスモデルとして注目されています。
実際の失敗事例から学ぶ|フランチャイズオーナーが陥りがちな罠
フランチャイズ経営の成功確率を高めるためには、成功法則を学ぶと同時に、「なぜ失敗したのか」という実際の事例から学ぶことが極めて重要です。
机上の空論ではなく、先輩オーナーたちが直面したリアルな失敗は、これから開業を目指すあなたにとって何よりの「予防薬」となります。
ここでは、フランチャイズオーナーが特に陥りやすい3つの典型的な失敗事例を挙げ、その背景にある原因と、あなたが同じ轍を踏まないための対策を具体的に解説します。
ケース1:本部からの紹介案件が途絶え、売上が激減
ハウスクリーニング業で独立したAさん。「開業当初は本部から安定的に顧客紹介があり、順調に売上を伸ばすことができました。
しかし半年が過ぎた頃、本部からの紹介がパタリと途絶え、売上が3分の1にまで激減。慌てて自分でチラシを配りましたが、時すでに遅し。運転資金が尽き、1年で廃業に追い込まれました」
- 失敗の罠:
このケースの罠は、「本部からの紹介が永続的に続く」という思い込みです。多くのフランチャイズ本部では、加盟店の事業を軌道に乗せるため、開業初期に集客サポートとして案件を優先的に紹介する制度を設けています。しかし、それはあくまでスタートダッシュを支援するための時限的な措置であることがほとんどです。 - 対策:
開業当初から本部からの紹介に100%依存するのではなく、必ず自力での集客活動を並行して行いましょう。売上が順調な時期にこそ、地域の情報誌への広告掲載やSNSでの情報発信、既存顧客へのリピート促進といった「次の顧客を獲得するための種まき」を継続することが、長期的に安定した経営を築くための生命線となります。契約前に、本部からの紹介制度の期間や条件を明確に確認することも不可欠です。
ケース2:近隣に同チェーンの店舗が出店され、顧客の奪い合いに
飲食店オーナーのBさん。「私の店は駅前の一等地で、開業以来、地域で一番の売上を誇っていました。
しかし2年後、本部がわずか500m先の商業施設に同じチェーンの店舗を出店。結果、お客様は分散し、売上は4割も減少。本部に抗議しましたが、『契約上問題ない』の一点張りでした」
- 失敗の罠:
これは、出店エリアの独占的な営業権を保証する「テリトリー権」が契約に含まれていなかったために起こる悲劇です。フランチャイズ本部の中には、ブランド全体の売上を最大化するために、加盟店同士の競合をいとわず近隣に出店させる戦略(ドミナント戦略)をとる場合があります。 - 対策:
契約書に「テリトリー権」に関する条項があるか、必ず確認してください。もし条項がない、あるいは内容が曖昧な場合は、契約を見送る勇気も必要です。具体的に「半径〇km以内には同チェーンの店舗を出店しない」といった明確な保証を書面で取り付けることが、自身の商圏を守るための重要な防御策となります。
ケース3:従業員の採用・育成に失敗し、オーナーが疲弊
コンビニエンスストアを経営するCさん。「人手不足でアルバイトが全く集まらず、やっと採用できてもすぐに辞めてしまう。
結局、私と妻が毎日14時間以上も店に立ち続ける生活が1年以上続きました。
売上はあっても、心身ともに疲弊しきってしまい、これ以上は続けられないと判断しました」
- 失敗の罠:
多くの未経験オーナーが見落としがちなのが、「人」に関する問題の深刻さです。特に店舗型のビジネスにおいて、従業員の採用と育成は経営の根幹をなす最重要課題です。この課題を軽視し、「誰でもいいから」と採用を妥協したり、育成を怠ったりすると、サービスの質の低下や離職率の増加を招き、最終的にはオーナー自身が現場の穴埋めに追われることになります。 - 対策:
開業計画の段階で、地域の最低賃金や求人倍率を調査し、現実的な人件費と採用計画を立てましょう。また、時給だけでなく、働きやすいシフト制度や明確な評価制度、オーナーとの良好なコミュニケーションなど、「この店で働きたい」と思わせる魅力的な職場環境を整えることが、優秀な人材を確保し、定着させるための鍵です。本部が提供する労務管理のサポートや研修制度を積極的に活用することも有効です。
フランチャイズで儲からないことに関するよくある質問(FAQ)
ここまでフランチャイズ経営の現実について詳しく解説してきましたが、それでもまだ個別の疑問や不安が残っている方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、開業希望者の方々から特に多く寄せられる「儲からない」というテーマに関連した3つの質問に対し、専門家の視点からQ&A形式で明確にお答えします。
Q1. オーナー自身が現場で働かないと儲からないのでしょうか?
A1. 必ずしもそうではありませんが、事業ステージによって関わり方は異なります。
フランチャイズオーナーの役割は、必ずしも「店長」として現場に立ち続けることだけではありません。最終的には、優秀なスタッフに現場を任せ、自身は経営戦略や多店舗展開に専念する「経営者」になることが理想形です。
しかし、特に開業初期においては、オーナー自身が現場の最前線に立つことには大きなメリットがあります。
- オペレーションの完全な把握:現場業務を自ら体験することで、ビジネスの流れや問題点を肌で理解し、的確な改善策を打てるようになります。
- 従業員との信頼関係構築:オーナーが汗を流す姿は、従業員のモチベーションを高め、強固な信頼関係を築く土台となります。
- 顧客の生の声を掴む:お客様との直接の対話から、サービスの改善点や新たなニーズといった貴重な情報を得ることができます。
事業が安定し、信頼できる右腕(店長)が育てば、徐々に現場を離れていくことは可能です。
ただし、「最初から現場には一切出ない」というスタンスでは、事業の細部を把握できず、的確な経営判断を下すのは難しいでしょう。
Q2. 儲かるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A2. 業種や規模によりますが、一般的には半年から1年を黒字化の目安と考えるのが現実的です。
開業してすぐに利益が出るほど甘い世界ではありません。
事業が赤字から黒字に転換するまでの期間は、ビジネスの損益分岐点売上高(経費と売上が等しくなる点)をいつ達成できるかによります。
この期間は、以下のような要因で大きく変動します。
- 業種の特性:無店舗型のハウスクリーニングなど初期投資が少ないビジネスは黒字化が早い傾向にあり、大規模な設備投資が必要な飲食店やフィットネスジムは時間がかかる傾向があります。
- 立地条件:集客力の高い一等地であれば、早期に売上目標を達成できる可能性があります。
- オーナーの経営努力:開業前の準備や開業後の集客活動、顧客満足度向上の取り組み次第で、黒字化までの期間は大幅に短縮できます。
重要なのは、事業計画の段階で「最低でも半年間は赤字でも事業を継続できる運転資金」を確保しておくことです。
短期的な収益に一喜一憂せず、腰を据えて事業を育てていく視点が求められます。
Q3. 自己資金はいくらあれば安心ですか?
A3. 「開業資金(初期費用)」に加えて、「最低6ヶ月分の運転資金」を合計した金額が、安心してスタートできる目安です。
フランチャイズの募集情報で「自己資金〇〇万円から可能!」と謳われている場合、その金額は多くの場合、加盟金や研修費といった「開業資金」の一部を指しているに過ぎません。
この金額だけで開業できると考えるのは非常に危険です。
安心して事業を運営するためには、以下の2種類の資金を明確に区別して準備する必要があります。
- 開業資金(初期費用):
事業をスタートするために、一度だけ必要となる資金です。
(例:加盟金、保証金、店舗取得費、内外装工事費、設備費、研修費など) - 運転資金:
事業を継続していくために、毎月必要となる資金です。
(例:人件費、家賃、水道光熱費、仕入れ費、広告宣伝費、ロイヤリティなど)
例えば、開業資金が300万円、毎月の運転資金が100万円かかるビジネスであれば、300万円+(100万円×6ヶ月分)=900万円が、安心してスタートを切るための自己資金の目安となります。
この基準を持つことで、開業後の資金繰りに窮するリスクを大幅に減らすことができます。
まとめ:フランチャイズは儲からない訳ではない!成功の鍵はオーナー自身の準備と覚悟
本記事を通じて、「フランチャイズオーナーは儲からない」という漠然とした不安の正体と、その裏側にある具体的な理由やリスクについて詳しく解説してきました。
結論として、フランチャイズビジネスは決して「儲からない事業」ではありません。むしろ、成功のノウハウが凝縮されたパッケージを活用することで、個人での独立開業に比べて失敗のリスクを大幅に抑えることができる、極めて合理的なビジネスモデルです。
しかし、その成功は決して約束されたものではありません。
フランチャイズで成功を収めるオーナーと、志半ばで撤退していくオーナーとの間には、明確な違いが存在します。
それは、フランチャイズという仕組みを正しく理解し、加盟する前の「準備」と、開業後の「覚悟」を持っているかどうかです。
- 信頼できる本部を徹底的に見極める準備
- 緻密な事業計画と、余裕を持った資金計画を立てる準備
- 本部任せにせず、自らの事業として主体的に経営する覚悟
- 地域に根差し、顧客と向き合い続ける覚悟
フランチャイズは、あなたを成功へと導く強力な「船」を提供してくれます。
しかし、その船をどこへ向かわせ、嵐を乗り越え、目的地にたどり着けるかどうかは、船長であるあなた自身の舵取りにかかっています。
「加盟すれば誰かが儲けさせてくれる」という他力本願の考えを捨て、自らの人生の経営者になるという強い覚悟を持つこと。
それこそが、「儲からないオーナー」で終わらないための、唯一かつ最も重要な成功の鍵なのです。